【行政書士試験】行政書士になる方法
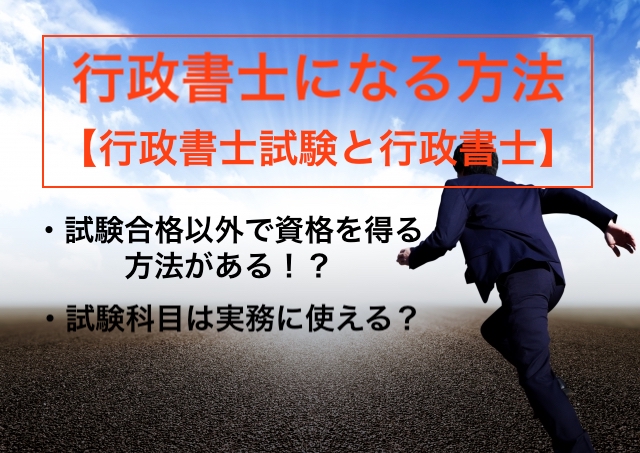
もうすぐ行政書士試験の時期なので、今回は行政書士と行政書士試験について書きたいと思います。
ちなみに、受験勉強などに関することは一切書いておりませんので、受験には全く役に立ちません。
行政書士になるには?
行政書士になるには、日本行政書士会連合会というところの名簿へ登録される必要があり、名簿に登録されるためには、行政書士の資格が必要となります。行政書士の資格については行政書士法第二条に記載があります。
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
行政書士試験に合格しなくても、行政書士として登録する方法があります。
まず、弁護士や税理士などの他士業から行政書士として登録する方法です。
他にも、長期間公務員として行政事務を行っていた方も、行政書士として登録可能です。公務員を定年後に、行政書士として登録されている先生も多くいらっしゃいます。
なお、以下の場合には、欠格事由となり行政書士資格を有することはできません。
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
未成年の方も受験可能ですが、成人になるまで登録できません。ちなみに、令和3年の最年少合格者は14歳だそうです。
行政書士試験について
行政書士試験は毎年1回、11月に行われます。
| 受験資格 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 |
| 受験料 | 10,400円 |
| 試験科目 | 行政書士の業務に関し必要な法令等 行政書士の業務に関連する一般知識等 |
| 合否判定基準 | 次の要件のいずれも満たした者を合格とする。 (1) 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者 (2) 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者 (3) 試験全体の得点が、180点以上である者 |
| 受験者数 | 令和元年:39,821人 令和2年:41,681人 令和3年:47,870人 |
| 合格者数 | 令和元年:4,571人(11.3%) 令和2年:4,470人(10.7%) 令和3年:5,353人(11.1%) |
・受験資格
行政書士試験は受験資格がありませんので、誰でも受験可能です。
・試験科目
『行政書士の業務に関し必要な法令等』
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
『行政書士の業務に関連する一般知識等』
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
・合否判定基準
合格者数に関わらず、180点以上取れば合格です。なお、合格判定基準⑶にあるように、一般知識で24点取れないと180点以上でも不合格になってしまいます。
行政書士試験の合格率
行政書士試験には毎年4,500〜5,000人程度合格しており、合格率は平均10〜11%です。
行政書士試験科目と実務
行政書士試験の科目と実務内容があまり関係ないと言われることがあります。
確かに、試験に合格したからといってすぐに実務ができるようにはなりませんが、行政書士の業務は多岐に渡るので、現在の試験科目は行政書士になるためには必要な知識です。
まとめ
今回は行政書士と行政書士試験について書かせていただきました。
試験を受けてから年月が経ってしまったので、試験勉強などについては割愛させていただきました。
行政書士試験に合格すれば、その合格は一生有効です。気が向いたら登録して、行政書士として働けます。
ただ、「試験に合格したらすぐに開業する!」なんて目標があればモチベーションが保てますが、ただ単に資格を取得するだけが目標だとモチベーションが上がらない方もいらっしゃるかと思います。
そんな時は、行政書士ができる業務を調べたりすると将来的に働いているイメージが持てて、モチベーションの維持に有効かもしれません。
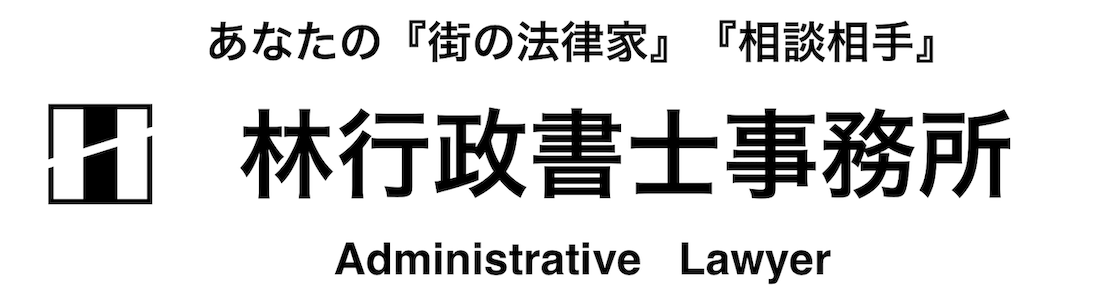


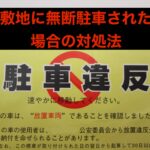
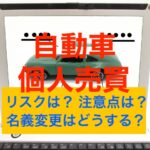
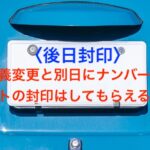

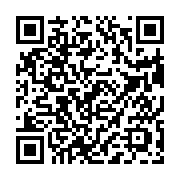
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません